※本記事には広告が含まれています。
こんにちは、しろこです。
拙ブログ『まるかて。』は観劇ブログではありませんが、すっかり観劇レポに押されています(自分のせい)。
今回も舞台レポです(『観劇』とはちょっと違う気がするので、あえて『舞台』レポ)。
『和』に関係するレポは、文楽と鼓童に続いて3回目。
今回お届けするのは、、、
石見神楽です!
「あんた、たまに全然毛色の違うもの観に行ってるよね…」という声がそこかしこから聞こえてきそうですが(^_^;)
昔、奈良県の平城宮跡で開催された天平たなばた祭りで上演されていた石見神楽を観ました。
いつだっけ…?と思ってネット検索したり、一緒に行った友人との過去のLINEを調べたりしたところ、2019年8月25日(日)のことでした(そこまで昔じゃなかった(;´∀`))。
(途中で天候不良により祭り自体が中止になって、ずぶ濡れになっててんやわんやで大阪まで帰った記憶が…)
祭りのために設置された仮設の舞台で上演されていた石見神楽。それを芝生広場の後ろの方から立ち見していた私たち。
遠目から観ていたにもかかわらず、衣装、舞、鳴り物、舞いながらの衣装替え(歌舞伎でいう『引き抜き』?)、そして何より、舞台に立っていたのが中学生か高校生かと思われる若者だったことに、友人ともども大興奮、そして感動でウルウル(これ、年取った証拠ですよね…。宝塚の初舞台生のダンスにも毎年ウルウルするし(;_;))。
石見神楽で唯一知っていた演目『大蛇』の前に大雨で祭りが中止になったため、観たのは知らない演目をほんの20~30分程度。
4人が剣を持って回りつつ舞いつつ衣装が変わっていく様子がすごく印象に残っていて、また観たいなぁ…と思った6年後(!)のある日、フリーペーパーで今回の公演『大阪・関西万博出演記念 高槻市・益田市姉妹都市交流公演 石見神楽』の小さい記事を発見。キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
が、公演日は8/1(金)。
月初めは仕事が…と思ったので(一応、真面目)、いつもなら即チケットを購入するところなのですが、数日考えることにしました(まだまだ残席あったし)。
でも、「いつか」は「今」。
翌日にはチケット購入(笑)
当日は会場のロビーに、ミニ大蛇と衣装が展示されていました。

益田市の特産品なども販売されていましたが、人が多い上に通路も狭くて軽くイラッとしたので(暑さは人をイライラさせます:笑)残念ながらスルー。
なぜそんなにごった返していたかというと、改札のすぐ横に物販があったからでしょうね。スペースに限りがあるとはいえ、そりゃ動線が悪くなりますよ。。。
(自分が客としていろんな劇場に行ったり、学生時代に舞台スタッフをやっていたことがあるので、見る目が厳しいしろこなのです(–))
開演は17:30、終演予定は20:30とのことだったので、仕事終わりに3時間、眠気に耐えられるか…と思いながら開演時間を迎えました。
・・・司会者がいる?
・・・益田市長と高槻市長の挨拶がある??
・・・
なんか、思ってたのと違う・・・?
と思ったのは最初だけ。
(益田市石見神楽神和会の会長さんの挨拶はユーモアがあって面白かったです)
いざ神楽が始まったら、眠気なんてどこへやら。前から5列目の席だったこともあり、迫力に圧倒されっぱなしでした。
上演されたのは『岩戸(いわと)』『十羅(じゅうら)』『大江山(おおえやま)』『八岐大蛇(やまたのおろち)』の4演目。
神話に興味はあるけれど、詳しいわけではない。
そのわりに、高千穂にも出雲にも戸隠にも行ったことがある私(「十分詳しいだろ!」と言われそうですが…。出雲に行った時は石見銀山まで足を伸ばしました☆)。
『十羅』以外の話の筋はそれなりに知っていました。
『岩戸』は、天の岩戸にお隠れになった天照大御神を、天之鈿女命らが囃子や舞で気を引き、岩戸から出そうとする話(ざっくりすぎてすみません^^;)。
(手力男命が押し開いた岩戸を投げ飛ばし、岩戸が飛んでいった先が戸隠といわれています)
最初に2柱の神様が登場するのですが・・・喋った!?
神楽って、台詞があったんですね…(天平たなばた祭りの神楽は舞の印象が強かったもので…。しかもあの時は、演出用か方言を喋っていたような…)。
台詞はもちろん現代語ではありませんが、言っていることは大体分かります(面の形によっては声がこもってちょっと聞き取りづらい)。
狂言の台詞と歌舞伎の台詞の間ぐらいの分かりやすさ(この説明が分かりにくいか…(;´Д`))。ちなみに私は、能の台詞はまったく分かりません。
2柱の神様が頑張っても岩戸は開かず、天之鈿女命が登場!
面をつけて着物のような衣装を着ていても分かる・・・スタイルの良さ(※舞手は全員、男性です)。
オガタマノキの実を模したとされる神楽鈴(棒にいっぱい鈴がついてるやつ)を持って舞うんですが、鳴らすべき時にだけ鈴が鳴る。それ以外の部分では、どういう振りをしていようが鳴りません。
もしかしたら鳴りにくいようにできている鈴(中の玉に重みがあるとか?)なのかもしれませんが、それならそれで、ちゃんとした音を出すにはしっかりと手首のスナップを効かせないとダメだろうし、いずれにせよ、たかが鈴、されど鈴なんじゃないかと思いました。
そして手力男命も登場。
しかし、私の席からはちょうど別の人(神様)の死角になって、舞台奥での演技がほとんど見えず…。心の中で「手前の神様ジャマー!」と思ってました(不敬)。
手前の神様が退いてからは(不敬)、天之鈿女命のしなやかな舞とはまったく違う、力強い舞を観ることができました。床を叩いて悔しがったり、衣装が変わったり、見ていて楽しかったです。
最後は、舞手の皆さんが面を取って素顔で舞います。
衣装から見えていた手の感じから、多分、天之鈿女命と手力男命は若い人が演ってるんだろうなとは思っていましたが・・・思った以上に若くてビックリ(@_@;) 高校…生…か…?
以前テレビで、石見神楽の部活がある高校が紹介されているのを偶然見ました。若者が「自分もやりたい!」と思って、実際に(多分誰もが)やれる環境があるって、特に伝統芸能の分野では他に類を見ないのではないかと思います。
続く演目『十羅』は、異国から攻めてくる鬼の彦羽根を、須佐之男命の末娘である十羅刹女が迎え撃つ…という話(これまたざっくり)。
この日上演された4作品中、唯一何の予備知識もなかったのですが、一番惹かれたのがこの『十羅』でした。
主役はもちろん、演目名にもなっている十羅刹女です。
(余談ですが、「十羅刹女」って、「10人」の「羅刹(鬼)」の「女」だから、言葉の分け方でいうと「十 羅刹女」だと思うんですが、なんで「十羅」という演目名なんでしょうね…。十二神将の伐折羅とか宮毘羅とか「羅」がついた神様が大勢いるので、「羅」に意味がある…? 羅漢とか迦楼羅も「羅」がついてる…)
でも、、、拙ブログの読者の方々は予想がつくと思いますが、私が惹かれたのは鬼のほう。
舞台作品でも映像作品でも、悪役が魅力的であればあるほど盛り上がるってなもんです!
福本清三が見事に斬られるから主役が引き立つんです!
私は、本当に怖いのは生きている人間だと思っているし、鬼には哀しみや憐れみを感じるので、鬼を「悪役」と言うのは本意ではないのですが、神 vs 鬼の話なので便宜上「悪役」ということにしておきます。
(なお、十羅刹女も元は悪い鬼でしたが、法華経の守護神になりました)
単独の舞も立ち回りも、とにかく激しい!
鬼の面には長い髪がついていて(ついているように見えるけど、実際どうなってるかは不明)、髪を振り乱しながら舞います。
きっと、頭をどう動かすと髪がどう動くかまで計算して演じているのだと思いますが、文字通り鬼気迫るものがありました。のたうち回る様もお見事。
もう・・・ね・・・鬼に勝ってほしいって思ったもん(笑)
十羅刹女には鬼とは違うカッコよさがありました。
同じ激しい舞でも、鬼は「動」の激しさ、十羅刹女は「静」の激しさというか(矛盾した表現ですが…)。
喩えるなら、前者は赤い炎、後者は青い炎。
石見神楽に限らず、伝統芸能で女性同士(「女性」と言っていいのか?)の戦いを描いた演目って珍しい気がします。
最後に十羅刹女は面を取るのですが、鬼は敗れてそのまま退場。
いや、まぁそういう話なんだけど、鬼のあの見事な舞をどんな方が演られていたのか見たかったなぁ。。。
次の『大江山』でも鬼役の方は顔出しなしでした。鬼は素顔をさらさないものなのかなぁ。。。
逆に、『大江山』では面をつけていない演者もいて、それはそれで新鮮でした。
この演目の見せ場はなんといっても、4人が剣を持って回りつつ舞いつつ衣装が変わっていく・・・
・・・あれ?
『4人が剣を持って回りつつ舞いつつ衣装が変わっていく・・・』
これ、あの時観たやつ・・・?
と、不思議な感覚を覚えながら観ていました。
・・・違いました(爆)
帰って調べたら、あの時観たのは『東大和』という演目だったようです。ちなみに演者は浜田市の長澤社中さん。
さて、この『大江山』ですが、様々な大江山伝説を元に時代劇や舞台が制作されていることからも分かるように、非常にストーリー性があり、起承転結がはっきりしています。
石見神楽の『大江山』は、源頼光が家臣の渡辺綱や坂田金時らを従えて、酒呑童子を討伐に行く話です(ざっくりに磨きがかかってきた)。
登場人物も多く、小道具もいろいろ使われていて、芝居としても面白い。そこに、立ち回りや先述した印象的な舞が加わるので、石見神楽の見どころが凝縮された演目の一つではないかと思いました。
でもやっぱり、石見神楽といえば『八岐大蛇』が有名ですよね(^_^;)
須佐之男命が大蛇を退治する話です(ざっくりの極み)。
『大蛇』が観たかったのに『大蛇』を観ることなく帰った天平たなばた祭りから6年。
ドキドキ・・・。
最後の演目の幕が上がると、大蛇たちが板付きでウネウネ。
な、長い・・・。
全部で8匹(8頭?8体?)もいるので、それぞれに個性がありました。
口を動かすのがうまい子(大蛇)とか、胴を動かすのがうまい子(大蛇)とか、とぐろを巻くのがうまい子(大蛇←しつこい)とか。
火を吹く大蛇をテレビで見たことがありますが、会場の関係か、今回の舞台では火は吹きませんでした。でも目は怪しげに赤く光っていて、迫力満点。
歌舞伎の見得のように、大蛇たちが姿勢を変えて静止するたびに拍手が起こりました。
おそらく和紙と骨組み(竹?)でできているのだと思いますが、なんせあの大きさ。しかも(これも文字通り)蛇腹だから、見た目の長さより実際はもっと長い。それを1人で操るには、技術だけでなく物理的な力と体力が相当必要だと思います。他の大蛇との共同作業もあるし、いいタイミングで頭も取らないといけないし(おっと失礼、須佐之男命が頭を斬り落とすんでした(笑))、神や鬼の舞とは違う大変さが伝わってきました。
7匹は頭を斬り落とされるだけですが、最後の1匹は頭を斬り落とされる前に、口に剣が刺さった状態でのたうち回ります。のたうち回るという点で『十羅』の鬼と相通じるものがあり、非常に惹き込まれました。
これがかの『大蛇』か・・・と、なんとも言えない高揚感がありました。
舞手のことばかり書いてきましたが、奏楽もすごかった!
何がすごいって、「よくこれだけの音を演奏し続けられるな…」って(声出しもあり)。
大太鼓は緩急をつけてリズムをリード、小太鼓と手拍子は一定のリズムを刻み続け、そして笛は・・・細かい音を吹き続けるっ!
数年だけ吹奏楽器をやっていた身からすると、信じられないぐらい吹き続けてました(驚愕)
特に『大蛇』の後半の奏楽は激しさMAX。舞人に負けず劣らずの運動量。
大太鼓の方は立ち上がる、小太鼓と手拍子の方は腕や首の筋が浮かび上がる、そして笛の方は・・・平然と吹いてる!?
そんなはずはないと思いますが、そう見えました。すごすぎ・・・。
スターダスト☆レビューのライブレポでも書いたとおり、亡くなったKANさんが
「スタレビですごいのは根本さん(Vo.)じゃない。100曲叩き続けられる寺田さん(Dr.)だ」
とおっしゃっていたようですが、舞台の一番端で演奏していた笛の方がもしかしたら一番すごいのかもしれない…(・・;)
『大江山』では、『岩戸』で天之鈿女命と手力男命を舞っていた方が奏楽をされていました。神楽界の二刀流ですね☆
なお、この公演の前日と前々日は大阪・関西万博で上演していたそうです。つまり3日連続での公演。なんかもう…ありがとうございます!
『八岐大蛇』で終演かと思っていたら、最後に白装束に烏帽子姿の複数の舞手が、まさに「神に捧げる舞」といった雰囲気で扇を手に何かに取り憑かれたように舞う、一種の神聖さを感じる舞がありました。
初めてちゃんと観た石見神楽。
神事に対して語弊があるかもしれませんが、エンターテインメント性が高く、美しく、かっこいい神楽でした。
終演後、ロビーに白装束姿の方が4名お見送りに出てこられたのですが、声を掛ける勇気がなく(小心者め…(T_T))、前を通る時に満面の笑みで拍手して失礼しました。
大げさではなく、「今日以上に食い入るように舞台を観て、今日以上に心を鷲掴みにされること、人生でもうないかもしれへん…」と思いながら帰りました。
それぐらいの衝撃でした。
(石見神楽に対する私の興味を6年間失わせなかった、あの時の長澤社中さんもすごい!)
石見神楽に関わる仕事ってどんなのがあるんだろ?と、思わずちょっとだけ求人検索をしたぐらいの衝撃でした。
5年間、わりとコンスタントにレポを書いていますが、どんなに有名な舞台を観ても、どんなに有名な人が出演していても、筆が進まないことがあります。
今回観た『大阪・関西万博出演記念 高槻市・益田市姉妹都市交流公演 石見神楽』
出演者に知っている人はもちろんいない、石見神楽自体、全国的に有名かと言われればお世辞にもそこまで有名とは言えない(と思う)、でも、書きたいことが次から次へと浮かんできました。
2019年に観た時も今回も、若い演者が多いという印象でした。
今回の公演を企画したMASUDAカグラボさんのウェブサイトや入場時にもらったチラシを読んで、石見神楽を広めようと積極的にいろいろな取組みを行っていることを知りました。
「伝統」と名のつくものについて考えると、どうしても金銭的な問題や時代の変化に起因する問題、継承することの難しさなど、マイナス面が頭をもたげてくると思います。
それに地元に根ざしていればいるほど、時間的な問題や精神的な問題もあるはず。
(私の地元(ど田舎)には「おとこし」「おんなし」という言葉があって、「婦人部」だの「婦人会」だのがあって、取り仕切ってるボスがいて、「おとこし」にも「おんなし」にも無言の同調圧力があります。限界集落になるほど住民が減った今でさえ、こうした空気は残っています)
伝統の中で新しいことをやろうとすると、ケチをつけたり待ったをかけたりする輩が出てくるでしょう。
会社でも学校でも、社会という組織には大して意味もなく、冷水を浴びせるのが趣味のような人々がいます。
一方で、一考の価値がある理由で異議を唱える人もいます。
歌舞伎や狂言など今も連綿と受け継がれている伝統芸能の世界には、新しいことに挑戦する若手と、それを認める柔軟な考えを持った師匠がいるのではないでしょうか。
そして誰かが物事の本質をないがしろにしそうになったら、ちゃんと手綱を引いて本人たちで軌道修正できるようにもっていっている気がします。
一度ガチガチに型にはまってみなければ、型を破ることはできません。
変わらない。でも変えていく。
それは決して時代に迎合しているわけではなく、観客に媚を売っているのでもなく、生き残るための戦略だと思うんです。
いくら知名度が上がっても、本質が伴っていなければいつか見向きもされなくなります。
逆に言えば、いくら(予想外の)エンターテインメント性を感じても、その中に揺るぎない何かを見て取ることができれば、私のように心を鷲掴みにされる人間も必ず出てきます。
『大阪・関西万博出演記念 高槻市・益田市姉妹都市交流公演 石見神楽』の演者の皆様、奏楽の皆様、スタッフの皆様、関係者の皆様、この度はいいものを観せていただきありがとうございました!
応援しております!!











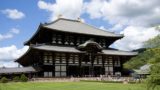


コメント