※本記事には広告が含まれています。
緊急事態宣言を受け、大阪公演が中止となった宙組『Hotel Svizra House(ホテル スヴィッツラ ハウス)』。GW最終日の5/5、梅田芸術劇場から無観客ライブ配信が行われました。
こんにちは、しろこです。
いつも観劇レポやライブレポを書くときは、観終わったテンションと勢いそのままに書き始めます。なんなら休憩時間中に、前半で良かったポイントだけメモったりしています。
特に印象に残らなかった公演や、( ・∀・)イイッ!!と思うポイントがほとんどなかった公演は、記事にすらしていません(笑)
無観客ライブ配信を観たのが5/5。
観劇レポを書き始めたのが5/10。
(そのため、引用した台詞の言い回しが実際と少々違う場合があります。ご了承ください。。)
いやー、なんというか、なんというか、うーん・・・う、うーん・・・
というのが観劇直後の感想だったのです(終演後の真風さんの挨拶でウルウルきたけど(T^T))。
悪いわけじゃないし素敵なシーンもあったけど、また観たいかと言われると、それはない、という感じ。決してディスってるわけではありません。ただの好みの問題です。
そんなわけで、観劇レポはスルーしようと思っていました。
でも、これほどまでに制作側の熱い想いがド直球な作品も珍しい。
たまたま制作上演が宝塚だっただけで、現状、舞台に携わる人は皆、本作に込められた想いに共感しかないでしょう。
文化芸術を愛する者の一人として、文化芸術が廃れるなんてあってはならない。
取るに足らないものとみなされることに強い憤りを感じる。
と、コロナがあろうがなかろうが、わりと日々淡々と生きている私にも、このところ熱い何かが腹の中で渦巻いているのであります。
ぐつぐつぐつぐつ・・・(煮)
「文化芸術?ふーん」という方に、微力ながら私もその魅力を伝えたい。
一応タイトルはホテル スヴィッツラ ハウスの【感想】としていますが、今回は自分の経験を踏まえた【考察】の意味合いが強い観劇レポでいきます。
参考情報
あらすじ
ナチスの台頭著しい第二次世界大戦中期。中立国であるスイスは”謀略の十字路”と呼ばれ、様々な国籍、階級、職業の人々が往来していた。そんなスイスのリゾート地サン・モリッツに佇むホテル スヴィッツラ ハウスには、戦火を逃れた富裕層が集っている。そこに新たな客が一人。名をロベルト・フォン・アムスベルクという。オランダ貴族の父とバレエ・リュスのダンサーを母に持つロンドン駐在の外交官であるが、それは表向きの顔。真の任務は英国情報部のスパイキャッチャーとして、敵国のスパイを摘発することであった。ロベルトはホテル スヴィッツラ ハウスを訪れた当日、ドイツ軍のパリ占領により失業したバレエダンサーのニーナと出会う。ホテルではロシアの亡命貴族ミハイロフ伯爵が主催するニジンスキー救済のチャリティ・バレエ公演が予定されており、ニーナはその公演で踊るためサン・モリッツへとやって来たのだった。同じ頃、この公演のスポンサーで、芸術家たちのパトロンでもあるオーストリアの実業家ヘルマン・クラウスナーも、若き未亡人アルマを伴いホテルを訪れる。戦争の影が覆うヨーロッパ。それぞれが抱える暗澹たる想い。そんな中でも、芸術を心から愛し、身の危険を犯してでもそれを守ろうとする者たちがいたーーー。
主な配役
ロベルト・フォン・アムスベルク:真風涼帆
ロンドン駐在のオランダの外交官
ニーナ・デュボワ:順花
元パリ・オペラ座のバレエダンサー
ヘルマン・クラウスナー:芹香斗亜
オーストリアの実業家。芸術家たちのパトロン
アルマ・ミュラー:遥羽らら
ポーランド出身の若き未亡人
マーサ・ウェリントン子爵夫人:万里柚美
サン・モリッツで療養中の英国マダム。息子を亡くしている
アレクサンドル・ド・ミハイロフ侯爵:寿 つかさ
バレエ公演を主催するロシアの亡命貴族
リチャード・ホールデン:美月 悠
英国情報部高官。ロベルトの上司
ユーリー・バシリエフ:桜木みなと
バレエ団の振付家兼ダンサー
バレエ・リュスとは
1909年にロシアの芸術監督セルゲイ・ディアギレフが創設したバレエ団。ニジンスキーやアンナ・パヴロワといった稀代のダンサーだけでなく、ピカソ、マティス、シャネル、ストラヴィンスキーなどの錚々たる芸術家が集結し、バレエを『総合芸術』に発展させた。才能ある芸術家を発掘し結びつけたディアギレフの手腕は、のちの芸術史に大きな功績を残すこととなる。
ニジンスキーとは
ロシアのバレエダンサー兼振付家(出身はウクライナ、両親はポーランド人)。高い跳躍力と表現力、極めて前衛的な振り付けを行ったことなどから、しばしば『伝説の』という形容詞がつく。バレエ・リュスで栄光を手にしたものの、第一次世界大戦中に精神を患い、のちに統合失調症と診断される(原因は戦争だけではなさそうだが)。1950年、ロンドンで死去。享年60歳。ニジンスキーが踊っている映像は残っておらず、このことが彼を伝説たらしめている部分も幾ばくかあるのかもしれない。
宝塚歌劇では、2011年に雪組で、ニジンスキーの半生を描いたミュージカル『ニジンスキー~奇跡の舞神~』を上演している。(主演:早霧せいな、会場:宝塚バウホール、日本青年館)
感想と考察
宝塚の完全オリジナル作品。
作・演出は植田景子氏。
文化芸術が果たす役割、意義を全面に訴える本作。登場人物の台詞に乗せてあまりにストレートに伝えるため、賛否両論あるかもしれない。
「今の宙組にあてて書いた」とのことであるが、文化芸術が置かれている昨今の状況を考えると、決して宙組だけのために書いたものでないことは明白である。
いきなり余談だが、宝塚の演出家にはウエダ氏が3人(植田紳爾、植田景子、上田久美子)、タニ氏が2人(谷正純、谷貴也)いてちょっとややこしい。
余談ついでに、主演の真風涼帆さんは、今作でも魅せたように、どこか色気があって知的でクールだけど熱いものを内に秘めた役が似合う。そこに茶目っ気まで加わった『オーシャンズ11』のダニー・オーシャンは、真風さんの真骨頂(しろこ談)。
閑話休題。
第二次世界大戦下の先行き不透明な時代。ナチスによる文化芸術への介入やユダヤ人迫害などが織り込まれており、セットも照明も全体的に暗い。宝塚の作品というより、アングラのよう。
ナチスが文化芸術をプロパガンダに利用したことやユダヤ人を迫害したことを知らなければ、ただのフィクションとしてしかみなされないかもしれない(後者はともかく、前者は知らない人もいるのではなかろうか) 。
ビリヤードキューを持ってのダンスや、劇中バレエ、偶然の出会いから結ばれるシーンなど、宝塚らしい演出も随所に見られた。
そして、オリジナル作品にありがちなご都合主義の展開もあった。特にラストは、「いや、そりゃあ諜報部員だって人間だけど、現実の世界ではこうはならないだろ」と思うある種のハッピーエンド。希望を見せるという意図なのだろうが。
「スペイン風邪で亡くなった」という台詞もあり、否が応でもこのコロナ禍を意識させられる。
物語の終盤、戦争に翻弄され、愛する者を亡くした人や明日をも知れぬ人々が次々と口にする台詞。
「芸術を絶やしてはならない」
「芸術は生きる希望である」
演出家や演者の想いは痛いほど伝わってきたが、個人的には、舞台に限らず映画でも本でも、伝えたいメッセージをそのまま台詞として登場人物に言わせてしまうのはいかがなものかと思う。一言二言ならともかく、あまりに言い過ぎると興ざめだ。
台詞という表面的なものに作品の意図全てが集約されることは、本来ない。
仕草や視線といった目に見えるものに加え、間や空気感のような、表面的なものの周りに絶えず存在する目に見えないものが司る部分は大きい。
本の場合は、地の文から想像を膨らませる。良い作家は、行間や情景を言葉だけで実に巧みに表現する。
1本の作品から何を受け取るかは、鑑賞者一人ひとり、読者一人ひとりに委ねられるべきだ。私は、『全世界が涙した』のようなキャッチコピーで売り込む作品を見ようとは思わない。
実際は「意味わかんなかった」という感想(?)で終わってしまう人もいるため、単純明快・単刀直入な作品も必要なのだろうが。
(なお、『娯楽作品』とは大衆受けする作品のことであるため、今回の『ホテル スヴィッツラ ハウス』は当てはまらない)
「観ている間は現実の辛いことを忘れられる」という台詞があった。
うつ病経験者から言わせてもらうと、それぐらい何かに没頭できる集中力があるときは、実はまだ大丈夫なのである。
本当に危険な精神状態のときは、何かを観ても読んでも、何も頭に入ってこない。私はうつ病と診断される1~2ヶ月前に母親と宝塚を観劇したが、観たことはなんとなく覚えていても、内容は全く覚えていない(自分で言うのもなんだが、記憶力はわりと良い人間なので、内容を覚えていないのは明らかに異常である)。
これは極めて極端な経験かもしれない。
しかしこの経験を経て今思うのは、私にとっての文化芸術とは、心の健康のバロメーターであるということだ。
作品に集中できるか(近くにマナーの悪い客が居て集中できないのは、また別の話)。
観劇中や読書中にふと他のこと(大抵は嫌なこと)が頭をよぎっても、自分の意志で作品の世界に戻ることができるか。
ほんの数時間日常から離れることで、定期的に心の栄養補給をしている。
『マリー・アントワネット』の観劇レポでも書いたが、私が舞台や本が好きなのは、作品の登場人物たちを通して、様々な人生を疑似体験できる気がするからである。反面教師にしたり、自分の人生の指標や糧にできる気がするのだ。
一人の人間が自分の人生で経験できることは限られている。たとえ波乱万丈の人生を歩んできた人でも、その期間は長くて100年。長く居を構えた場所にいたっては、片手で数えられるほどしかないだろう。
フィクションでもノンフィクションでも、起こったことに対して、なぜそうなったのか、それは短期的・長期的にどのような経過を辿ったのか、立場による見方の違いはどうだったのか、といったことを知っているだけで、現実に起こった問題に対する気構えが変わることもある(ノンフィクションの場合は、歴史<を>学ぶのではなく、歴史<から>学ぶ必要がある)。
舞台が数千年前のどこかの国でも、宇宙でも、いち家庭であっても同じことだ。
どうあがいても、時にはなるようにしかならないこともあるのだと、ふいに悟ることもある。
登場人物の誰かに感情移入したり、第三者の視点やいわゆる『神の視点』で作品に関わることで、自分にとって大切なものがあるように相手にも大切なものがあることや、それぞれに事情や言い分があることも見えてくる。
探していた答えや何かのきっかけとなるものに出会えることもある。
はっきりとはわからなくても引っ掛かる言葉がある。あとになって点と点が線で繋がるように、おぼろげだったものの輪郭が見えてくることもある。
感性を磨く、と言うと具体性に欠けるだろうか。
想像力を養う・・・と言っても同じことか。
抽象的な作品でも、ともすれば駄作と言われるような作品であっても、自分なりに吟味し解釈することで、自分の人生に何らかの形で取り入れることができるのではないだろうか。
何かを見出すこともできるのではないだろうか。
うまく言葉では表現できない感情や想いを、誰もが持っている。よほどの聖人君子でない限り、子供でも大人でも、ドロドロした何かが心の中に巣くっているはずだ。
それを映し出し、自分の中にもたしかにある負の部分に目を向けるきっかけを与えてくれるのもまた、文化芸術である。
一人で沈思黙考する時間が人間には必要である。
元来賛否両論があるテーマは、意見が拮抗するものだ。
災害や病気のように、自分の身に降りかかって初めてわかることだってある。
文化芸術というと高尚なものと捉えられがちだが、マンガやアニメだって立派な文化芸術だ。音楽やダンスの習い事だって、文化芸術の一端である。
本、歌、芝居、絵画、マンガ、アニメ、なんでもいい。
何かに共感したり、次の展開が気になって仕方がなかったり、悔しさや楽しさを感じたり、そうした経験が一度でもあるかどうかで、文化芸術に対する考え方は変わってくると思う。
文化芸術など何の役に立つのか。
芸術で腹は膨れない。
その意見に異論はない。
だが心が豊かになることはたしかにある。
初めて聴くはずの曲に、懐旧の情を覚えることもある。
ほんの数分の出来事が心に深く刻み込まれ、一生忘れることのないものとなりうるのである。
ーーーーーーーーーーー
終演後の真風さんの挨拶。
「今日ほどお客様のありがたさを身に染みて感じたことはありません」
本来ならば拍手が起こるはずの場面での静寂。
客席にしか身を置いたことがない人間ですら、その数秒の静寂に言い知れぬ寂しさを感じた。
舞台に立ってこれまで実際に拍手を浴びてきた方々にとっては、感慨もひとしおだったであろうことは想像に難くない。
このまま文化芸術が廃れていいはずがない。
廃れさせては、決していけない。














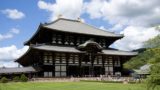











コメント